◾️ 本記事は一部プロモーションを含んでいます
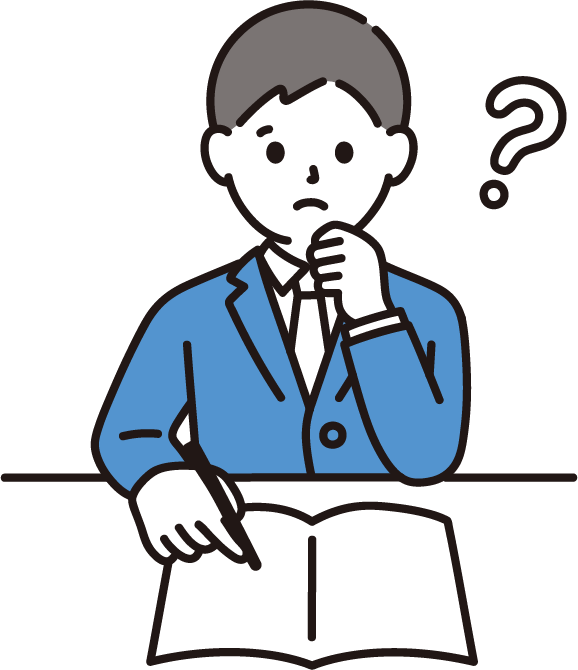
参考書選びで失敗したくない…合格に近づく参考書の選び方と使い方を教えてください!
予備校に通わず参考書だけで勉強する自宅浪人生にとって、参考書選びは合格を左右する最重要ポイントです。
この記事を読むことで、あなたに合った参考書の選び方と、「合格に近づく」使い方が分かります。
記事の内容
- 自宅浪人生に参考書選びが重要な理由
- 【失敗しない】宅浪の参考書選びの基準3つ
- 【STEP形式】志望校から逆算した参考書ルートの作り方
- 成績が100%上がる参考書の使い方5選
- 【科目別】国立理系で実際に使った参考書全公開
- 【Q&A】参考書に関する10の疑問
私の自宅浪人経験
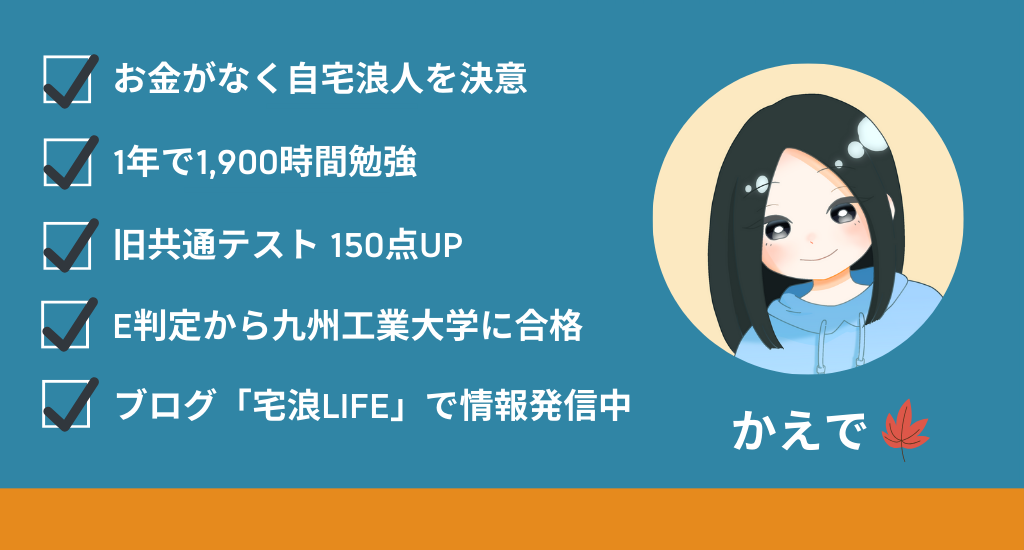
実体験に基づいた「宅浪完全ガイド」はこちら:【2025年最新】宅浪とは?成功率37.5%の真実と失敗しない5つの方法
自宅浪人生に参考書選びが重要な理由

予備校生と宅浪生の最大の違いは「プロ講師の授業があるかないか」です。
予備校生は年間100万円を払ってプロ講師の授業を受けています。宅浪生にとってその代わりとなるものが、参考書です。
宅浪における参考書の役割
- 先生の代わり:分かりやすい解説で理解を深める
- カリキュラムの代わり:何をどの順番で学ぶか示してくれる
- 演習問題の宝庫:問題を解くことで本番に対応する
- モチベーション維持:進捗が見えてやる気が続く
つまり、宅浪生にとって参考書は「合格への地図」です。
参考書だけで本当に合格できるの?
結論から言うと、参考書だけで十分合格できます。私自身、予備校に通わず参考書だけで、E判定から逆転合格しました。
さらに、2025年現在、ChatGPTやスタディサプリなど参考書学習をサポートするツールが充実しており、宅浪でも予備校生と十分に戦える時代になっています。
【失敗しない】宅浪の参考書選びの基準3つ

参考書選びで失敗すると、時間とお金を無駄にするだけでなく、モチベーションまで下がります。以下の3つの基準を参考に、絶対に失敗しない参考書選びを実行しましょう。
基準①:現在の学力レベルに合った参考書を選ぶ
最も重要な基準です。「○○大学合格者が使ってた」という理由だけで参考書を選ぶのは危険です。
✕ 偏差値45なのに「東大数学で1点でも多く取る方法」を購入
◯ 偏差値45なら「基礎問題精講」から始める
難しすぎる参考書を選ぶと以下の問題が起こります。
- 解説が理解できず挫折する
- 基礎が抜けたまま応用に進んでしまう
- 本番で基礎問題を落として不合格
難しい参考書に手をつけると、「賢くなった気」になりますが、逆に効率が悪いです。まずは、しっかり基礎を固めることで、応用問題や過去問を解くときに一気に力がつきます。
自分のレベルの見極め方
以下の方法で現在の学力を把握しましょう。
- 現役時代の模試結果を確認
- 共通テスト過去問を1年分解いてみる
- 志望校の過去問を1年分解いてみる
- 本屋で実際に参考書を読んで理解度をチェック
重要:レベルが合わない参考書は、どれだけ評判が良くても「あなたには合わない」参考書です。
基準②:1年間使い続けたい参考書か見極める
参考書は1年間のあなたのパートナーです。何周もしたくなるぐらい「モチベーションが上がる」参考書を選びましょう。
チェックすべきポイント
- 解説の分かりやすさ:自分にとって理解しやすい解説か
- レイアウト:読みやすいか
- デザイン:毎日開きたくなるデザインか
- 紙質・サイズ:書き込みやすいか、持ち運びやすいか
- 新品 or 中古:モチベーションが上がるのはどちらか
「この参考書なら毎日開きたい」と思える1冊を選びましょう。見た目が気に入らない参考書は、どれだけ内容が良くても挫折しやすいです。
本屋で実物を確認しよう
ネットのレビューだけで判断せず、必ず本屋で実物を手に取って確認しましょう。5分ほど立ち読みして、自分に合うか確かめてください。
確認後はネットで購入すればポイントも貯まります。ただし、「新品の参考書を本屋で購入した」という行動自体がモチベーションになる人は、本屋での購入もおすすめです。
基準③:1科目1分野1冊の原則を守る
宅浪初心者のよくある失敗が「参考書の大量購入」です。
✕ 数学だけで5冊購入し、全部中途半端
◯ 青チャート1冊を完璧にしてから次へ
参考書をたくさん買うと「賢くなった気」になりますが、実際は以下の問題が起こります。
- 繰り返し解かないため基礎力がつかない
- どれも中途半端で力にならない
- モチベーションが低下する
- お金が無駄になる
複数の参考書に手を出すより、1冊を完璧にする方が10倍成績が上がります。これは私が宅浪で学んだ最も重要な教訓です。
1科目1分野1冊とは?
「1科目1冊」といっても、分野ごとに参考書が必要な場合があります。例えば英語なら以下のように分けます。
- 単語:データベース4500(1冊)
- 文法:Vintage(1冊)
- 長文:やっておきたい英語長文300(1冊)
重要なのは、1つの分野に対して同時に使うのは1冊ということです。単語帳を3冊並行したり、文法書を複数同時に使ったりするのはNGです。
レベル違いの参考書への移行はOK
ただし、1冊を完璧にした後、レベルの違う参考書に進むのはアリです。
例:化学の場合
基礎問題精講を完璧にする(基礎期)
→ 重要問題集に進む(応用期)
→ 過去問演習(実践期)
これは「レベルアップ」なので問題ありません。避けるべきは、同じレベルの参考書を複数同時に使うことです。
宅浪の参考書購入ルール
- 同時に使うのは1分野1冊:同じ分野・同じレベルの参考書を複数並行しない
- レベルアップは歓迎:1冊を完璧にしたら、より難しい参考書に進んでOK
- 購入前に自問:「この参考書を完璧にしたら確実に合格できるか?」
- 完璧にしてから次へ:使用中の参考書を完璧にしてから次を買う
「なんとなく良さそう」で買わず、本当に必要な参考書だけを厳選しましょう。
【実戦】志望校から逆算した参考書ルートの作り方

志望校から逆算した参考書ルートの作ることで、自分が今使うべき参考書を明確にしましょう。
STEP①:志望校のレベルと出題傾向を確認
まずは、ゴールを明確にします。
- 志望校の過去問3年分を見る
- どのレベルの問題が出るか確認
- 頻出分野をメモ
- 合格最低点を調べる
例:「九州工業大学の数学は青チャートレベル。二次試験では微積分が頻出」
STEP②:現在の学力と志望校のギャップを確認
志望校の過去問を1年分解いて、現在の実力を把握します。
- 何割取れたか
- どの分野が弱いか
- 基礎・応用のどちらが不足しているか
例:「過去問は2割しか取れない。基礎から固め直す必要がある」
STEP③:1年を3期間に分割する
宅浪の1年間を以下のように分割します。
- 基礎期(例:4月〜7月) = 基礎を徹底的に叩き込む
- 応用期(例:8月〜10月) = 応用問題への対応力をつける
- 実践期(例:11月〜3月) = ひたすら過去問演習
基礎が全くできていない人は、基礎期を長めに取るなど自分に合ったスケジュールを立てましょう。
STEP④:各期間に使う参考書を割り振る
それぞれの期間に最適な参考書を配置します。
数学の参考書ルート例
基礎期(4月〜7月)
青チャート数学IA・IIB・III
→ 1冊を最低3周、完璧にする
応用期(8月〜10月)
・青チャートの復習(忘れた範囲のみ)
・共通テスト対策問題集
→ 共通テスト形式に慣れる
実践期(11月〜3月)
・共通テスト過去問6年分
・志望校の赤本8年分
→ 本番形式で演習
STEP⑤:1冊あたりの計画を立てる
参考書は最低3〜5周する前提で計画を立てます。
例:青チャート数学IIIを4ヶ月で5周する計画
- 1周目:2ヶ月(1日5問ペース)
- 2周目:1ヶ月(1日10問ペース)
- 3周目:2週間(苦手問題のみ)
- 4〜5周目:1週間ずつ(総復習)
この計画をゴールから発想する「合格手帳 」に書き込んで管理しましょう。
参考書ルート作成で迷ったら
自分で参考書ルートを作るのが難しい場合は、以下を活用しましょう。
- ChatGPT:「○○大学合格のための数学の参考書ルートを教えて」と質問
- UniLink:難関大生に参考書ルートを相談できるアプリを活用
- ネット検索:「○○大学 参考書ルート」で検索
【宅浪必見】成績が100%上がる参考書の使い方5選

良い参考書を選んでも、使い方が間違っていたら意味がありません。以下の5つの方法を確実に実践しましょう。
使い方①:1冊を最低5周する【最重要】
複数の参考書に手を出すのではなく、1冊を完璧にすることで力がつきます。
青チャートを1周しただけで、本番で全く同じ問題が出たとき、確実に解ける自信はありますか?
おそらく自信がないはずです。なぜなら、1周では定着しないからです。
なぜ5周必要なのか
- 1周目:問題と解法を知る
- 2周目:解法を思い出しながら解く
- 3周目:自力で解けるか確認
- 4周目:スピードアップ
- 5周目:完璧に定着
5周すれば、同じ問題はもちろん、応用問題も解けるようになります。これが参考書学習の最大のメリットです。以下のペースを参考に復習しましょう。
- 1問解いたら → 翌日復習
- 2周目 → 3日後に復習
- 3周目 → 1週間後に復習
- 4周目 → 2週間後に復習
- 5周目 → 1ヶ月後に復習
この間隔が記憶の定着に最適です。詳しくは【科学的に正しい】超効率的な勉強法で解説しています。
使い方②:問題の上に解いた日付を書き込む
各問題の上に、解いた日付を書き込みましょう。最後にいつ復習したか一目で分かるようにするためです。
例:問題番号の横に「4/15, 4/18, 4/25, 5/2, 5/16」と書く
こうすることで、
- 復習のタイミングが分かる
- 何周したか一目で分かる
- 日付が増えていくとモチベーションが上がる
- 参考書に愛着が湧く
ちなみに、私の青チャートは日付だらけでボロボロでした。それが努力の証になります。
使い方③:参考書に直接書き込む【ノート不要】
参考書は「自分だけの最強の教科書」にしましょう。綺麗に使うのではなく、どんどん書き込んでください。
何を書き込めばいいのか
- なぜ分からないのか:「公式を忘れてた」「計算ミス」など
- 調べた内容:ChatGPTで調べた解説を追記
- 暗記の語呂合わせ:自分だけの覚え方
- 別解:こっちの方が早い解法
- 注意点:「ここでよくミスする」など
ノートに綺麗にまとめるのは時間の無駄です。参考書に直接書き込んで、その参考書だけ見れば全てが分かる状態にしましょう。
綺麗な参考書はカッコ悪い
宅浪で成功する人の参考書は、みんなボロボロです。書き込みだらけで、ページがよれよれになっています。それが「この参考書と1年間戦った証」です。
綺麗な参考書は、使っていない証拠。恥ずかしがらずにどんどん書き込みましょう。
使い方④:分からない問題はChatGPTで即解決
宅浪生の最大の悩みが「分からない問題を質問できる人がいない」ことです。しかし、2025年現在はChatGPTという最強の先生がいます。
ChatGPTの活用方法
- 問題の解説を依頼:「この問題の解き方を教えて」
- なぜそうなるのか質問:「なぜこの公式を使うの?」
- 別解を聞く:「もっと簡単な解き方はある?」
- 類題を作ってもらう:「似た問題を3問作って」
ChatGPTは無料で使えて、24時間いつでも質問できるため、予備校の質問コーナーより便利です。
質問の前に5分考える
すぐにChatGPTに質問するのではなく、まず5分は自分で考えましょう。自分で考える過程が最も力をつけるからです。
5分考えて分からなければ、ChatGPTに質問 → 理解したら参考書に書き込む、という流れが最強です。
使い方⑤:参考書で範囲は「スタディサプリ」を活用
参考書の解説だけでは理解できない範囲が出てくることもあります。そんな時は、動画授業で補完しましょう。
【公式】スタディサプリ高校・大学受験講座なら、月額約2,000円でプロ講師の授業が見放題です。予備校の1/50の価格で、基礎から難関大レベルまで対応しています。
スタディサプリの使い方
- 基本:参考書ベースで勉強を進める
- 理解できない範囲だけ:該当範囲の授業を見る
- 倍速再生:1.5倍速で効率的に
- 復習:授業内容を参考書に書き込む
全ての授業を見る必要はありません。参考書学習の補助として、必要な部分だけ活用しましょう。
有料サービスには抵抗があるかもしれませんが、予備校は年間100万円なのでコスパ最強です。参考書だけで不安な人は検討してみてください。
【国立理系】宅浪時代に実際に使用した参考書を公開

私が、E判定から九州工業大学に合格するまでに使用した参考書を、時期別に全て公開します。結果として、共通テストは683点(76%)、二次試験は700点(88%)でした。
数学:青チャート中心で基礎を徹底
基礎期(4月~7月)
青チャート数学IA(確率のみ)
青チャート数学IIB(ベクトル/数列のみ)
青チャート数学III(全範囲)
→ 二次試験で出題される内容に絞って対策
→ 各5周以上、完璧にした
応用期(8月~10月)
緑チャート(共通テスト対策)
合格る計算 数学III(計算スピードUP)
→ 青チャートも定期的に復習
実践期(11月~3月)
共通テスト赤本 数学
実戦問題集 数学IA

実戦問題集 数学IIB(10年分)
九州工業大学 赤本
→ 分からない範囲は青チャートに戻って復習
物理:漆原シリーズで基礎から応用まで
基礎期(4月~7月)
漆原の物理 明快解法講座
→ めちゃくちゃ分かりやすい神参考書
→ 7周して完璧にした
応用期(8月~10月)

漆原の物理 最強の99題
マーク式問題集(共通テスト対策)
→ 応用力がついた
実践期(11月~3月)
化学:鎌田シリーズで理解してから演習
基礎期(4月~7月)
鎌田の理論化学の講義

鎌田の有機化学の講義
基礎問題精講

リードα化学基礎+化学
→ 化学は完全にゼロからスタート
→ 鎌田シリーズを読み込んで理解してから問題演習
応用期(8月~10月)
実践期(11月~3月)
重要問題集の復習(3周)
共通テスト赤本・

実戦問題集
九州工業大学 赤本
英語:単語・文法・長文をバランスよく
基礎期(4月~7月)
データベース 4500(単語)
Vintage(文法)

やっておきたい英語長文300(音読)
→ 単語は毎日100個ずつ復習
→ 長文は音読で定着
応用期(8月~10月)
基礎期の参考書の復習
レベル別問題集4 中級編
実践期(11月~3月)
国語:8月から本格スタート
応用期(8月~10月)
ゴロゴ古文単語
古文ヤマのヤマ
漢文ヤマのヤマ
マーク式問題集
→ 基礎期は理系科目に集中するため国語は後回し
実践期(11月~3月)
地理:黄本1冊で対策
応用期(8月~10月)

地理総合、地理探究の点数が面白いほどとれる本(黄本)
→ 3周して知識を定着
実践期(11月~3月)
参考書購入のコツ
本屋で実物を確認 → Amazonや楽天市場
で購入が、ポイントが貯まるためおすすめです。過去問や実戦問題集は使用回数が少ないので、メルカリでの購入もおすすめです。
【Q&A】参考書に関する10の疑問

参考書についてよくある質問をまとめました。
Q1. 結局、参考書は何周すればいいの?
最低3〜5周、理想は7周以上です。「問題を見た瞬間に解法が浮かぶ」レベルまで繰り返しましょう。回数より「完璧に理解できたか」が重要です。
Q2. 参考書は新品と中古どっちがおすすめ?
基本は新品、過去問は中古でOKです。1年間使う参考書は「自分で選んだ新品」の方がモチベーションが上がります。赤本や実戦問題集は使用回数が少ないので中古で十分です。
Q3. 参考書はいつ買えばいいの?
基礎用は4月中、過去問は4月〜5月です。過去問は秋になると売り切れることが多いので、早めに購入しましょう。ただし、使うのは11月以降でOKです。
Q4. 参考書だけで本当に合格できる?
はい、十分合格できます。私も参考書だけでE判定から逆転合格しました。ただし、理解できない範囲はスタディサプリで補完するのがおすすめです。
Q5. 参考書選びで失敗したらどうすればいい?
すぐに変更しましょう。「もったいない」と思って使い続けても時間の無駄です。ただし、1週間は使ってみて判断してください。最初は難しく感じても、慣れると理解できることもあります。
Q6. 複数の参考書を並行して使ってもいい?
基本的にNGです。1冊を完璧にしてから次に進みましょう。例外として、単語帳と文法書など、役割が異なる参考書の併用はOKです。
Q7. 高校時代の参考書を使ってもいい?
モチベーションが上がるなら使ってOKです。ただし、「高校時代の自分」を引きずらないよう注意。新しい気持ちでスタートしたいなら新品を買いましょう。
Q8. 参考書の選び方が分からない時はどうすればいい?
以下の方法で相談しましょう。
- ChatGPT:「○○大学合格のための数学の参考書を教えて」
- UniLink:難関大生に直接質問
- ネット検索:「○○大学 おすすめ参考書」で検索
Q9. 参考書学習のモチベーションを保つコツは?
以下の方法が効果的です。
- 日付を書いて周回数を見える化
- 1冊終わるごとに自分にご褒美
- 合格手帳に進捗を記録
- 参考書がボロボロになることを楽しむ
- 定期的に模試を受けて成長を実感
Q10. 参考書の費用を節約する方法はありますか?
以下の方法で節約できます。
【まとめ】参考書を味方にして宅浪を成功させよう

宅浪生にとって参考書は「最強の先生」です。正しく選び、正しく使えば、予備校生にも負けない実力がつきます。
この記事の重要ポイント
- 参考書選び:自分のレベルに合った参考書を、本屋で実物確認してから購入
- 参考書ルート:志望校から逆算して、基礎→応用→実践の流れを作る
- 使い方:1冊を最低5周、日付を書き込み、参考書に直接書き込む
- 補助ツール:ChatGPTで質問、スタディサプリで補完
私はこの方法でE判定から逆転合格しました。あなたにもできます。
ただし、参考書だけではモチベーション維持が難しい人もいます。そんな時は、予備校の無料体験を受けてやる気をもらったり、病まない対策を実践してメンタルを整えることも大切です。
参考書を武器に、宅浪で成功しましょう。
あなたの宅浪LIFEを応援しています。
次に読むべき記事
宅浪の成功率って、ぶっちゃけどのくらい?
何から始めたらいいか分からない...
宅浪で絶対に失敗しない方法は?
予備校と宅浪は結局どっちがいいの?
宅浪で本当に大丈夫?成功体験が知りたい...
お金がない...宅浪に役立つ無料サービスは?
👆 これらの疑問をすべて解決
宅浪でE判定から合格した体験談をもとに、無料の「宅浪完全ガイド」をつくりました。
宅浪完全ガイドで解決できること
✔️ 宅浪の成功率「37.5%」の真実
✔️ E判定から合格したリアル体験談
✔️ 宅浪vs予備校の徹底比較データ
✔️ 成功者と失敗者の決定的違い
✔️ 宅浪で失敗しない5つのコツ
✔️ 宅浪成功に導くサービス5選
✔️ 宅浪開始前にやるべきこと20項目
✔️ よくある質問10選とその回答
これらの情報を知らずに宅浪を始めるのは、もったいないです
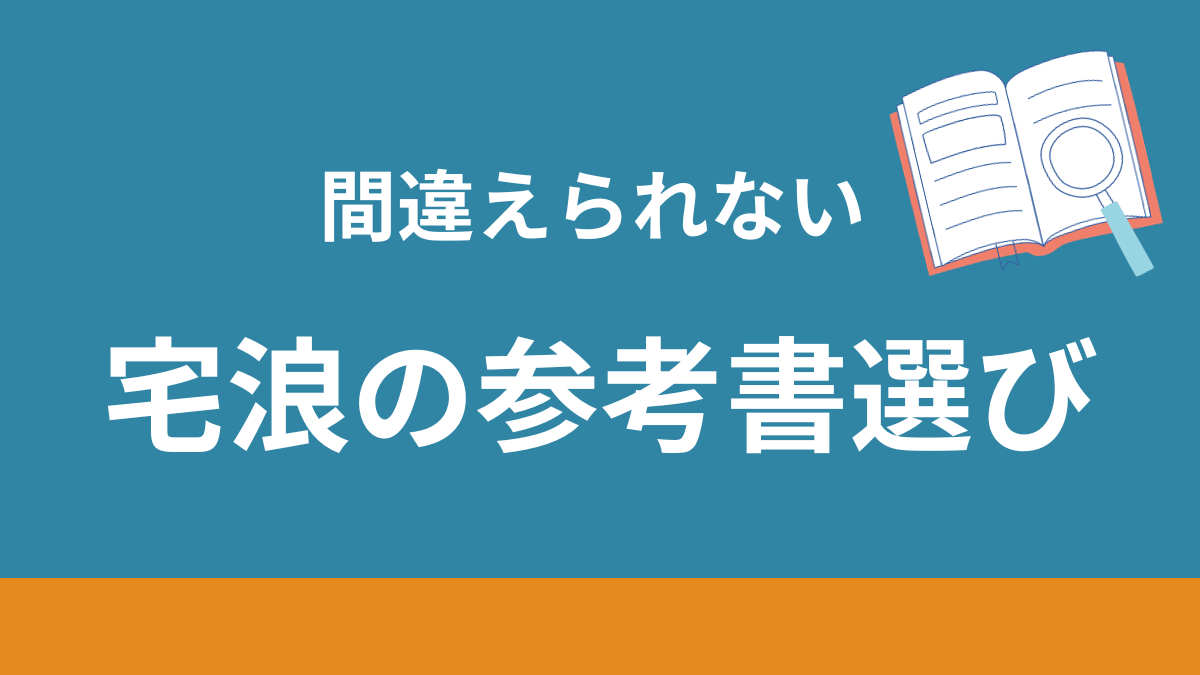


お気軽にコメントをどうぞ